アロマにハマっていくと、いろんなことをやってみたくなりますよね。
精油の効能とか、作用とか、どんな時にどの精油を使ってみたらいいのか・・・。
自分にはもちろんのこと、家族やお友達、もしかしたら職業にするかもしれませんし、、、精油の使い方は無限大にあって本当に無限な世界です。
しかし、自分では解決できないことになってしまったら、、、、。
そんなことを思ったことはありませんか?
ここではこれからアロマを楽しんでいくうえで知っていきたい法律を紹介していきます。
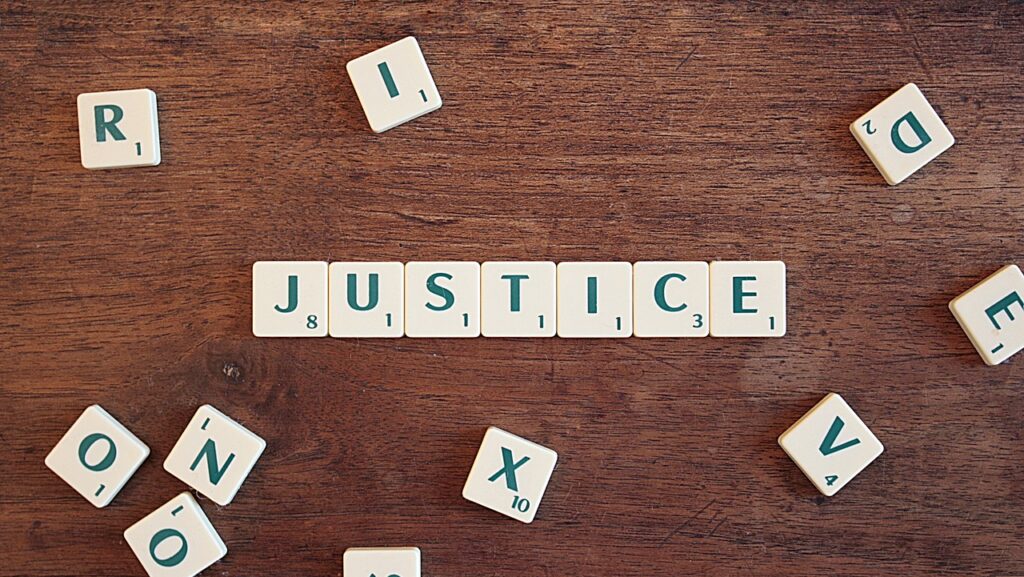
基本的に自己責任の原則
医薬品医療機器等法により医薬品、医薬部外品を無許可で業として製造し、これを授与することは禁止されています。
しかし、『自分が使用するために、自分で化粧品を作る』ことは規制されていません。
わかりやすく言うと、自分が製造して使用した結果で生じた問題については自分で責任を取ることになりますよということになります。
アロマを自宅で行う場合には、いつもこの『自己責任の原則』の考えが前提にあって行うことを忘れないでください。

医薬品医療機器等法
正式名称は『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』(以下、医薬品医療機器等法と表記)です。
これは薬事法が改正されてもので、平成26年11月25日に施行されました。
この医薬品医療機器等法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の製造、製造販売(市場への出荷や流通)、販売やそれらの取り扱いについて規制する法律になります。
医薬品、医薬部外品、化粧品と誤解しないようにする
アロマで使用する精油は医薬品医療機器等法上の『医薬品』、『医薬部外品』、『化粧品』のいずれにも当てはまりません。
規制対象外の雑貨扱いになります。
効能、効果を謳うのは医薬品医療機器等法違反
例えばのお話です。
「ラベンダーの精油は不眠症に効果がある」や、「ティートリーはニキビが治る」と言って精油を販売したり授与したりすることは無認証無許可医薬品等の販売・授与になり、医薬品医療機器等法違反にあたります。
行政の許可がなく業として化粧品を製造することは医薬品医療機器等違反
製造業の許可を得ずに化粧品を製造することは、化粧品の無許可製造になり、医薬品医療機器等法違反になります。
これは小分けをするという行為も該当します。
また、医薬品、医薬部外品についても同じことが当てはまります。
第13条(製造業の許可)
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない(第1項)。
※「製造」には、小分けを含む(医薬品医療機器等法第1条の4参照)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)より
ここまで目を通してくると、ちょっと気になることがありませんか?
先ほどの製造業の許可を考えると、家族にアロマスプレーを作ったり、友人のハンドクリームを作ってプレゼントすることも当てはまってしまうのでは???と心配になるかもしれませんが、ここは大丈夫です。
日本アロマ環境協会では、違反しているとは言い切れないと判断し、次のことに気をつければプレゼントは可能だとしています。
第13条の『業として』とは、反復継続して特定多数の人に供給する目的を持って製造することをいい、家族や特定の友人にプレゼントすることは『業として』製造することにあたらないと判断する。
また、普段化粧品店やドラックストアなどで販売されている化粧品は、法律の規制を受けて製造・輸入したものです。
しかし、手作りの化粧品は規制を受けて製造された物ではなく、品質や安全性については自らの責任によることになります。
プレゼントをするときには、相手に『自己責任』を自覚したうえで受け取ってもらえるよう、十分に説明をして注意を促す必要があります。
例えば、どの精油を使ったのか、プレゼントするものの使い方の説明ができるようにしましょう。
その際にはラベル使って製作日や使用期限、使用した精油を記載して貼っておくとより◎です。
また、手作り化粧品によって危害やトラブルが生じたときには製造物責任およびその他の民事上の責任を問われる可能性がありますので十分注意しましょう。
医師法
医師の免許制度、業務上の業務などを規定した法律で、医師以外の者が医業を行うことを禁止しています。
また、アロマでのトリートメントにおいて診察行為をしてはいけません。
トリートメントを家族や友人に行う場合、受け手である心身の健康状態について知り得ることもありますが、その症状を診て病名を診断したり、本来ならば医師が行うような治療と紛らわしい行為を行ってはいけません。
当然ながら、医薬品の許可を受けていない精油を薬のように使用することもできないことを頭に入れておいてください。
獣医師法
獣医師の免許制度、業務上の義務などを規定した法律になります。
アロマのトリートメントでは動物の診察行為をしてはいけません。
一方で、ケアやトリミングなどは国家資格に属するものではないため、この分野でのアロマを行うことは違反行為に当たりません。
最近ではペットを対象としたアロマの商品が増え、実際にペットにアロマを行う機会が増えています。
しかしながら、ペットである動物と人間の身体の仕組みは異なります。
ペットに対するアロマを行う際には人間の独りよがりな考えでアロマをしないようにしましょう。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(略称:あはき師法)
あはき師法は、それぞれの免許のないものがあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうなどの医療行為を業として行うことを禁止しています。
アロマのトリートメントとよく似たマッサージがありますが、マッサージを業としたいのであれば国家資格であるあん摩マッサージ指圧師の免許が必要になります。
あはき法では免許のない者があん摩やマッサージ、指圧、はり、きゅうなどの医療に似た行為を業として行うことを禁止していますが、エステティックやカイロプラクティック整体などもマッサージに似た行為が行われています。
これらの行為とマッサージ師の行うマッサージやあん摩、指圧との区別は、必ずしも明確ではありません。
製造物責任法(PL法)
製造物責任法とは、消費者の保護と救済を目的に消費者が製造物の欠陥により損害を生命や身体、財産に係る損害を生じたことを明らかにすれば、その製造物や輸入業者に対して損害賠償責任を求めることができるようにした法律です。
近年ではアロマに関する保険や保証があり、必要に応じて加入してみるのも良いでしょう。
ここではいくつかの保証や保険を紹介します。
- アロマテラピー保険(アロマテラピー賠償責任補償制度)
日本アロマ環境協会(AEAJ)
日本アロマ環境協会の個人正会員ならば誰でも加入することができる保険です。
保険料は毎年の年会費に含まれているため、別途費用は必要ありません。
https://www.aromakankyo.or.jp/admission/compensation/
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
事業者が実際のものよりも著しく優良な品質や、著しく有利な価格を表示したり、過大な景品類を提供して、消費者の自主的かつ合理的な選択を妨げる行為を制限したり、禁止することを指します。
消費者としても、精油を購入したりトリートメントを受けるときなどに『最高品質』と言った表示を鵜呑みにしたり、SNSで見つけた情報だけで判断したりするのではなく、店頭やアロマの専門家に質問したり、文献を調べたり、自分で使うことでの経験を積み重ねていくうえで、自分に合ったものやサービスを見つけていくことが重要です。
消防法
火災の予防や危険物の貯蔵、取り扱いなどについて定めた法律です。
消防法では、指定数量以上の危険物を貯蔵所以外の場所で取り扱ったりすることを禁止しています。
私たち個人が自宅でアロマを楽しむ程度の精油の量であれば、法的な規制を受けることはありませんので心配する必要はありません。
しかし、精油は揮発する特性を持っており、火気に近づけると引火する可能性が高いものです。
火災を予防するためにもアロマキャンドルなどの利用のときはもちろんのこと、保管、取り扱いには十分な注意が必要です。
